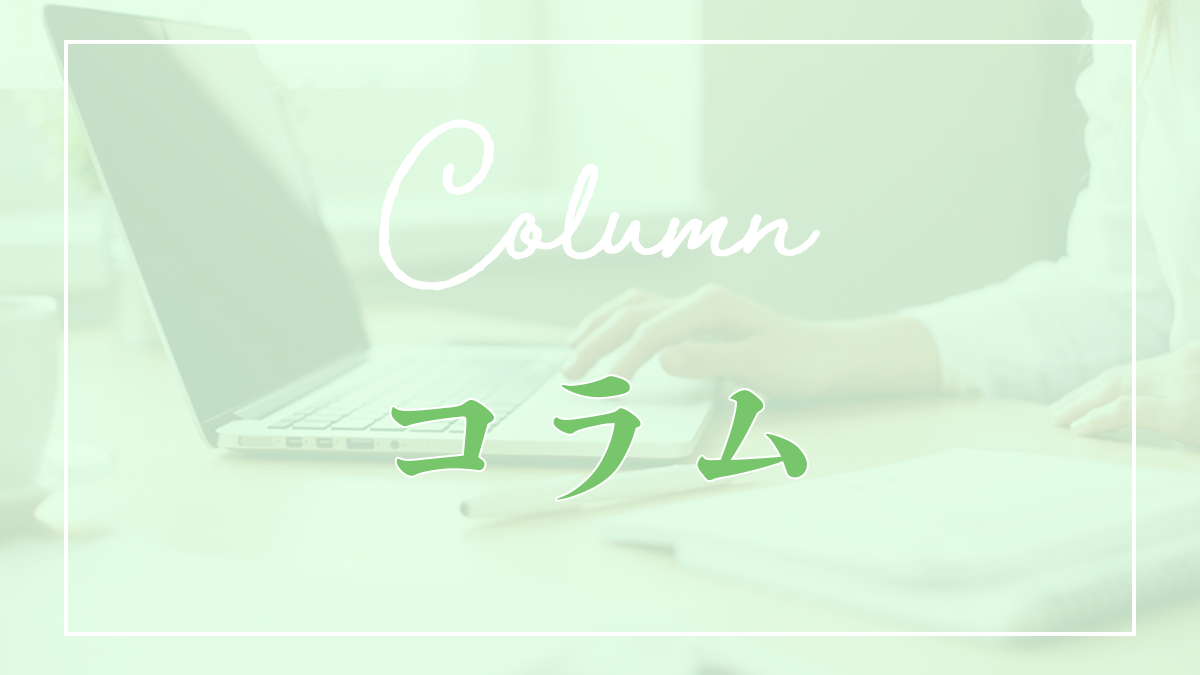「福利厚生を充実させたのに効果が感じられない」「社内イベントを増やしてもエンゲージメントが上がらない」
そんな声が聞かれる背景には、エンゲージメントに対する誤解があります。
エンゲージメントとは単なる「満足度」でも「楽しさ」でもなく、
社員が組織や仕事に対して主体的に貢献しようとする心理的なつながりを指します。
🔹 エンゲージメントの特性①:一時的な楽しさでは高まらない
社員旅行やレクリエーションなどの「楽しい時間」は一時的な高揚を生みますが、それが持続的なエンゲージメント向上に直結するとは限りません。
エンゲージメントは「一緒に働くことの意味」や「自分の仕事が組織にどう貢献しているか」という内面的な納得感により形成されます。
したがって、イベント施策を行う際も「何のために実施するのか」を明確に伝えることが重要です。
🔹 エンゲージメントの特性②:成果主義だけではつながらない
「目標達成意欲が高い=エンゲージメントが高い」と考えられがちですが、成果のために「義務的に」頑張る状態は、いずれ燃え尽きにつながります。
エンゲージメントが高い人は、成果へのプレッシャーではなく、仕事そのものに意義を感じ、自発的に行動している状態にあります。
つまり、「外発的動機づけ(報酬・評価)」よりも、「内発的動機づけ(やりがい・共感)」が重要なのです。
🔹 エンゲージメントの特性③:関係性の質が影響する
エンゲージメントは個人の努力だけでなく、上司や同僚との信頼関係・心理的安全性に大きく左右されます。
たとえ仕事がハードでも、「相談できる仲間がいる」「自分の意見が尊重される」と感じられる環境では、社員は安心して挑戦し、組織への帰属意識を高めていきます。
🔹 エンゲージメントの特性④:理念やビジョンの共有が土台になる
エンゲージメントを高める根幹は、会社の存在意義(Purpose)や理念への共感です。
社員一人ひとりが「この会社の目指す方向に自分も関わりたい」と思えるかどうかが鍵になります。
そのため、経営層や管理職は、日常的に理念を語り、業務の中で「理念を体現する行動」を称える文化を育むことが大切です。
🔹 まとめ:エンゲージメントを高める3つの実践ポイント
- 仕事の意義を共有する
→「なぜこの仕事をするのか」「誰の役に立っているのか」を明確にする。 - 信頼関係と心理的安全性を醸成する
→ ミスを責めずに対話を促し、安心して意見が言える職場をつくる。 - 理念やビジョンを“現場の言葉”で語る
→ 方針説明や評価面談の際に、理念と日常業務を結びつけて話す。
💬 社労士からのひとこと
エンゲージメントは“職場の空気”のようなもの。
見えにくいですが、確実に組織の生産性や離職率に影響します。
制度やイベントを整えるだけでなく、【社員一人ひとりが「この会社で働く意味」を感じられる職場づくり】が、本当のエンゲージメント向上につながります。