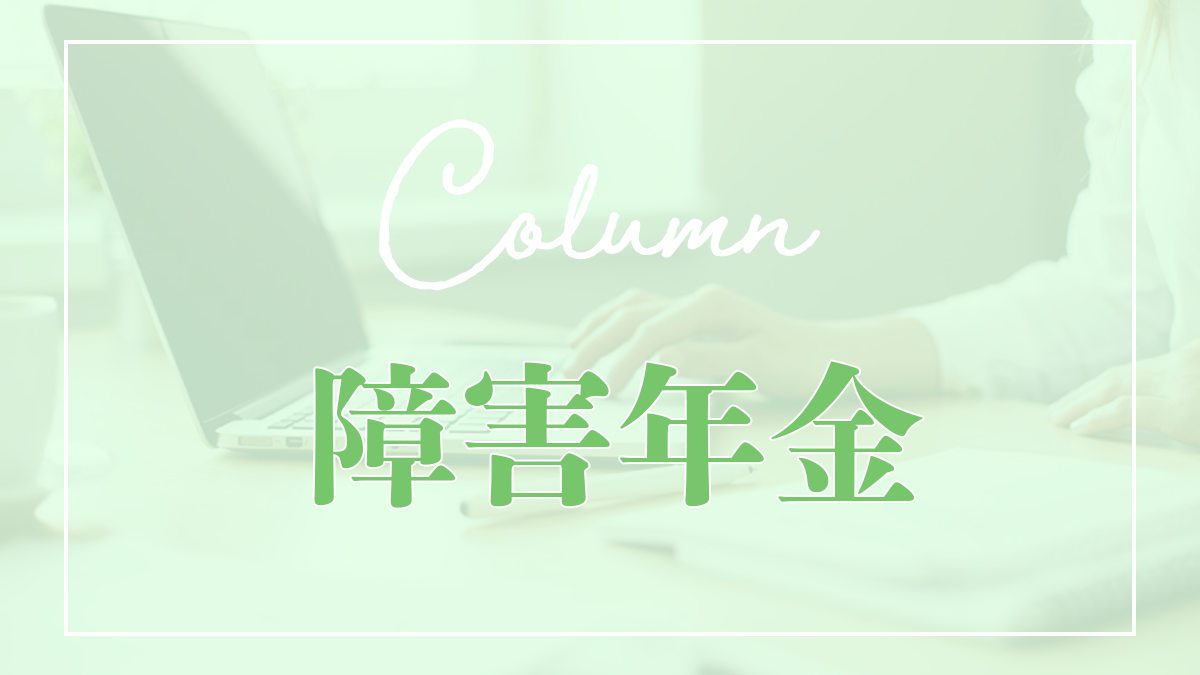日本年金機構は、令和6年度に実施した障害年金の認定状況の調査結果を受けて、精神障害・知的障害・発達障害の「不支給」とされた事案の点検を進めています。
その結果、令和6年7月までの不支給事案のうち 124件(約4.3%)が支給決定に変更 されました。
■ 背景
令和6年度から、障害年金の不支給割合が急増しており、特に精神障害の不支給率が前年の6.4%から12.1%へ上昇しました。
その多くが「障害等級の目安より下位等級で認定されたこと」が理由とされており、適正な判定がなされていたかが課題となっていました。
これを受け、日本年金機構では令和6年度以降の不支給事案について、複数の認定医による再審査や認定プロセスの見直しを実施しています。
■ 見直しで重視されるポイント
今回の点検では、従来よりも以下のような要素を重視して判断が行われています。
- 病状・状態像:症状の経過・予後(長期療養・再発傾向など)をより重視
- 療養状況:入院歴・薬物治療の内容・治療継続の有無を考慮
- 生活環境:対人関係・社会的支援の有無・家庭や職場での援助状況を重視
- 就労状況:職場での配慮・勤務日数・就労が生活に与える影響を評価
- 障害種別ごとの見直し例
- 精神障害:症状経過と生活制限を重視
- 知的障害:不慣れな環境下での援助の必要性を重視
- 発達障害:対人関係・意思疎通に基づく援助必要性を重視
■ 今後の対応
年金機構は、令和6年度以降の不支給事案(約11,000件)について、月2,000件のペースで年内に点検を進める方針を示しています。
また、今後は「支給されたが等級が低すぎる」といった事案も順次見直される予定です。
■ 社労士からのアドバイス
今回の報告は、障害年金の認定が「再評価される可能性がある」ことを示しています。
とくに精神障害・発達障害・知的障害の方で、
- 不支給決定に納得できない
- 症状が長期化・悪化している
- 日常生活に大きな支障がある
といった場合は、再審査請求や再度の申請を検討することも有効と考えられます。
障害年金の審査では、診断書の記載内容や日常生活の具体的な様子の伝え方が非常に重要です。
必要に応じて、社労士が医師との情報共有や書類作成のサポートを行うことも可能です。
ご自身やご家族が該当する場合、現在の状態や資料を確認のうえ、再申請・再審査の可能性についてご相談ください。